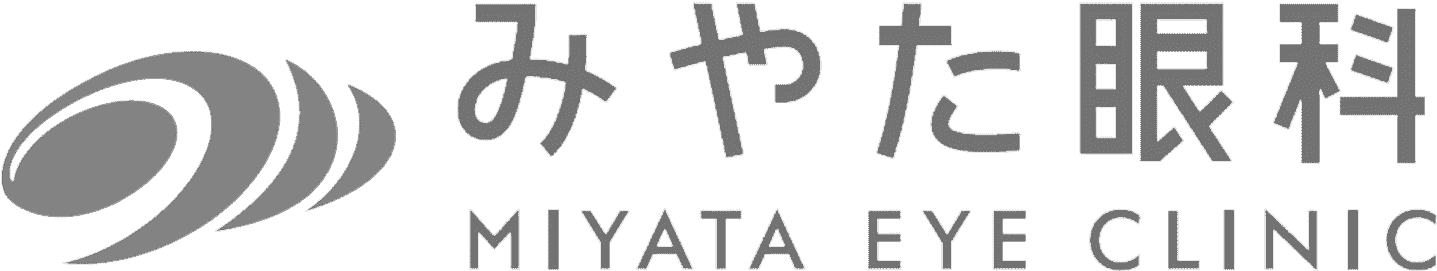加齢黄斑変性
加齢黄斑変性とは?
黄斑疾患には近年話題の加齢黄斑変性をはじめとする血管新生黄斑症や黄斑円孔、黄斑前膜、中心性網膜炎、遺伝性黄斑変性、など多々あります。それらの中から加齢黄斑変性についてです。
加齢黄斑変性は、網膜の中心部である黄斑が加齢に伴って障害される疾患で、世界中の高齢者の視力低下や失明の原因となっています。
全世界で2020年には約1億9600万人がAMDを患っており、2040年には約2億8800万人に増加すると予測されています。日本では50歳以上の人口に占めるAMDの発生頻度は1.3%とされており、約70万人が患者と推定されています。年齢が高くなるほど発症率が増加し、特に滲出型加齢黄斑変性(nAMD)は高齢者で増加しています。日本人ではポリープ状脈絡膜血管症(PCV)が高頻度に観察され、ヨーロッパ人に比べてPCVの割合が高いことが特徴です。
症状
黄斑という、眼底の網膜(カメラでいうとフィルム)の中心で、ものを見るために大切で、視力に最も影響の大きいところに障害が現れる病気です。
いろんなタイプがあるので一概には言えませんが、典型的な症状としては、中心が見えにくく歪んでみえる(変視症)、中心が暗く見えたり、黒い点が見えたり(中心暗点)、色の識別が難しくなるなど、視野の中心が障害されます。そうなると見たいと思うところ、つまり中心視力が低下してしまい、真っ暗になることはないのですが進行してしまうと社会的失明に至ることがあります。
原因・発症リスク
網膜の代謝を行い、古くなった細胞を排泄してくれるお掃除細胞がありますが、その細胞の働きが加齢により悪くなるといわれています。
そうなると、網膜のお掃除ができないので老化が進みやすくなり、代謝の悪い場所では、加齢黄斑変性という病気の発症リスクがあがるといわれてきました。
発症リスクとして有名なのは、日光暴露や喫煙があります。
紫外線などによる活性酸素や食生活・環境悪化による活性酸素の増加、その他遺伝など、まだ解明されていないことも多く研究が続けられています。
喫煙による酸化ストレスが眼に蓄積すると、加齢黄斑変性の背景にある炎症を引き起こすといわれています。発症予防や、発症してしまった方が進行を遅らせるためには、禁煙が非常に重要です。
TVやパソコンによる光刺激を受ける機会が非常に多くなったことも近年の患者増加の原因と考えられています。
その他、最近では栄養状態(ビタミン、カロテン、亜鉛の不足)が関係していることも示唆されており、サプリメントの内服をお勧めする場合もあります。
*加齢による黄斑部の老廃物の蓄積
*生活習慣: 光刺激、喫煙、偏った食生活
*特定の遺伝子の関与が考えられている。(CFH遺伝子/ARMS2遺伝子/HTRA1遺伝子等)
分類
・滲出型(wet type)
脈絡膜から新生血管が発生し、出血やむくみを引き起こします。急激な視力低下が特徴です。
・萎縮型(dry type)
網膜色素上皮細胞の萎縮により、視力低下が緩やかに進行します。
治療
光線力学的療法(PDT)と抗VEGF薬の硝子体内注射、レーザー光凝固があります。
抗VEGF薬の眼内注射は、原因である新生血管の発育を促進する因子(VEGF)の働きを阻害し、新生血管の形成を阻止或いは抑制を図ります。効果は按手しており、現在の治療の主流になっていますが、効きにくい方もいらっしゃるので複数回の注射を必要とすることもあります。症例によっては従来のレーザー光凝固で新生血管を焼いて治療します。光線力学療法(PDT)は光に反応する薬剤を用いて新生血管を閉塞します。
抗VEGF薬の進化や新生血管型に対する点眼薬開発などが期待されています。
予防
*喫煙はリスクを高めるため、禁煙が推奨されます。
*サングラスの使用: 太陽光を避けるためにサングラスをかけることが推奨されます。
*バランスの良い食事: ルテインや抗酸化ビタミンを含む食事が推奨されます。
黄斑部の疾患は視力の回復が難しい病気が多く、早い段階での治療が大切です。そのため視力の低下や変視症(歪んで見える)、中心暗点(真ん中が暗く見える)などの症状が出たら、早めの受診をお勧めします。